常設展
総合展示
(1)しまねの夜明け(~旧石器時代)
人類の発生から、現生人類に至る過程を通し、島根県最古の人類の痕跡を紹介します。

旧石器(原田遺跡)
(2)しまねの旧石器人と縄文人(旧石器~縄文時代)
気候の変動による海面の上昇や動植物の変化によって、人々の生活が大きく変わっていったことを、移動生活をしていた旧石器時代と定住生活をしていた縄文時代と比較しながら紹介します。

土偶(下山遺跡)

三瓶山埋没杉と丸木舟(三田谷遺跡)
(3)邪馬台国時代のしまね(弥生時代)
紀元前3世紀、大陸から稲作と一緒に新しい文化や技術が入ってきます。稲作文化や鉄器が伝わったルートを想定しながら、弥生文化の特色を紹介します。

人面付十器(西川津遺跡)

◆重要展示:王墓墳誕生四隅突出型墳丘墓西谷3号模型
(4)大和朝廷と出雲・隠岐(古墳~奈良時代)
古墳時代から奈良時代、島根には古代国家の中心であった近畿地方の文化が入ってきます。一方で、島根には国家の一地域としての役割が与えられ、ここに中央と地方の関係が生まれます。この国家形成に動きのなかで島根の人々の生活がどのように変わったかを探ります。

隠伎国木簡レプリカ(平城京出土)

◆重要展示:神秘の輝き古代出雲の玉作り
(5)尼子氏と益田氏と石見銀山(平安~安土桃山時代)
律令制社会から荘園社会への移行にあたり、律令の遺産を継承して新しい制度が運用されました。また、人や物の往来も盛んになり都市が形成され、交易を通じ中国・朝鮮など海外の物資も流入するようになりました。この当時の地域の状況を紹介します。

◆重要展示:輝き世界へ石見銀山御取納丁銀
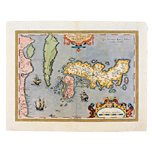
ティセラ日本図
(6)近世しまねのブランド戦略(江戸時代)
「たたら製鉄」など、地域独自の風土と原料を活かして華開いた近世島根の産業から生まれた富によって新しい文化が創造されていった様子をご紹介します。
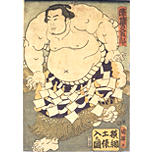
横綱土俵入之図 陣幕久五郎の図(国輝

◆重要展示:鉄の炎島根のたたら
(7)日本の面影 しまね(明治時代~)
小泉八雲の目に映った近代の島根の様子を、八雲の著書や記述にまつわる資料を通してご紹介します。

一畑電車と北松江駅復元模型

小泉八雲著「知られぬ日本の面影」初版本